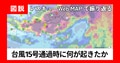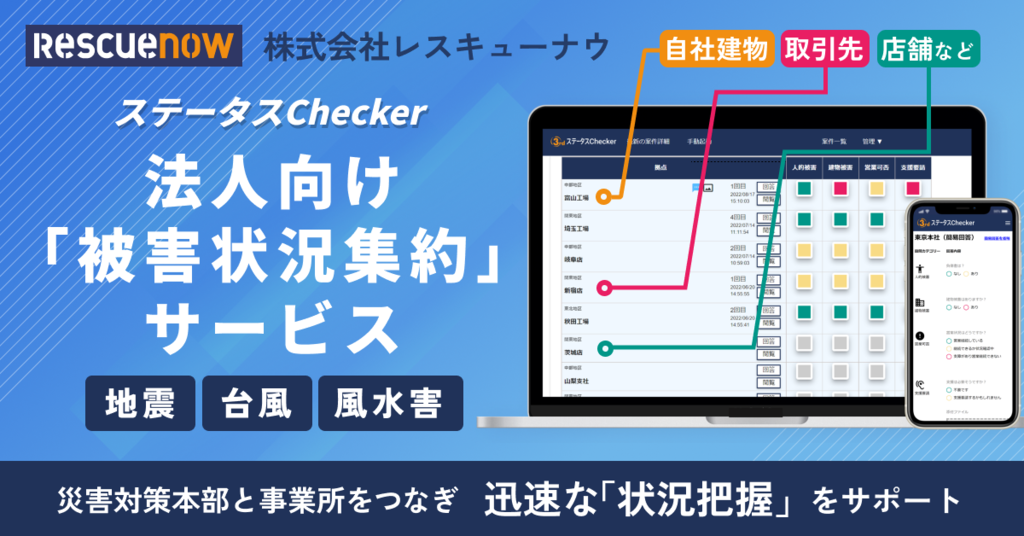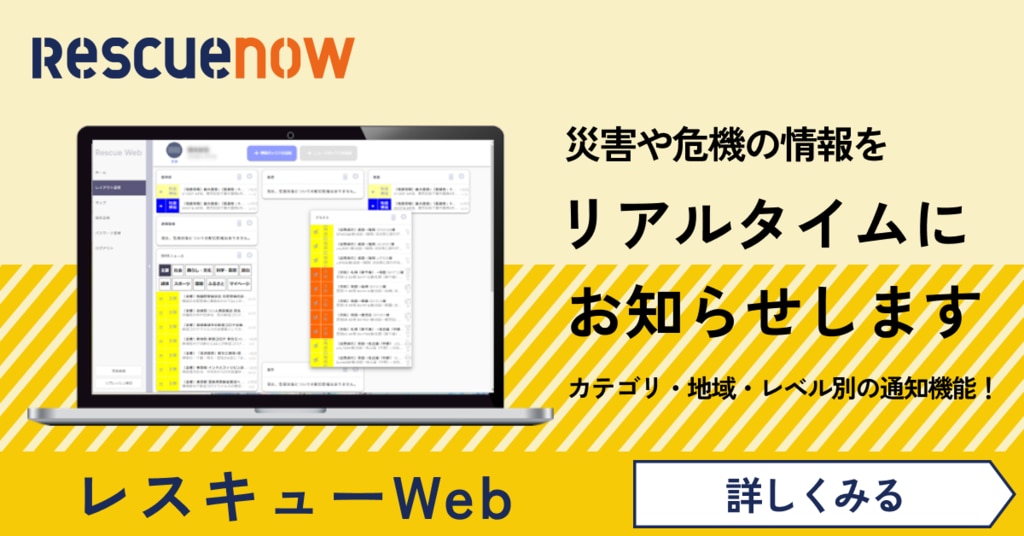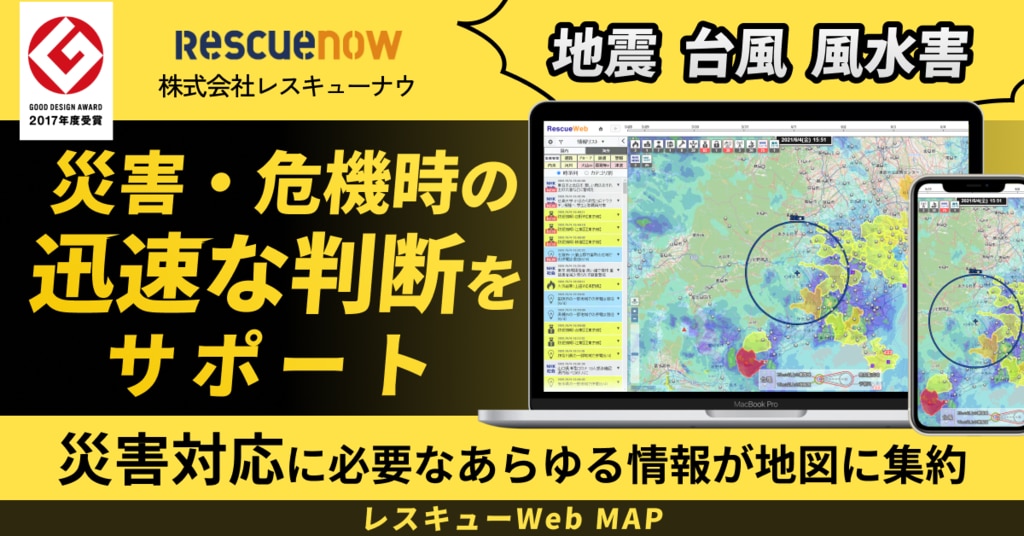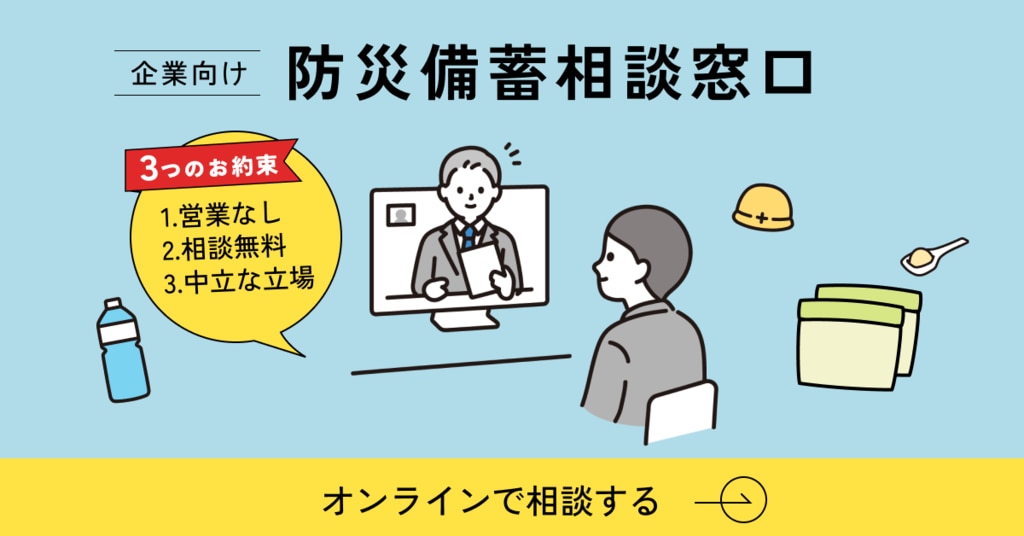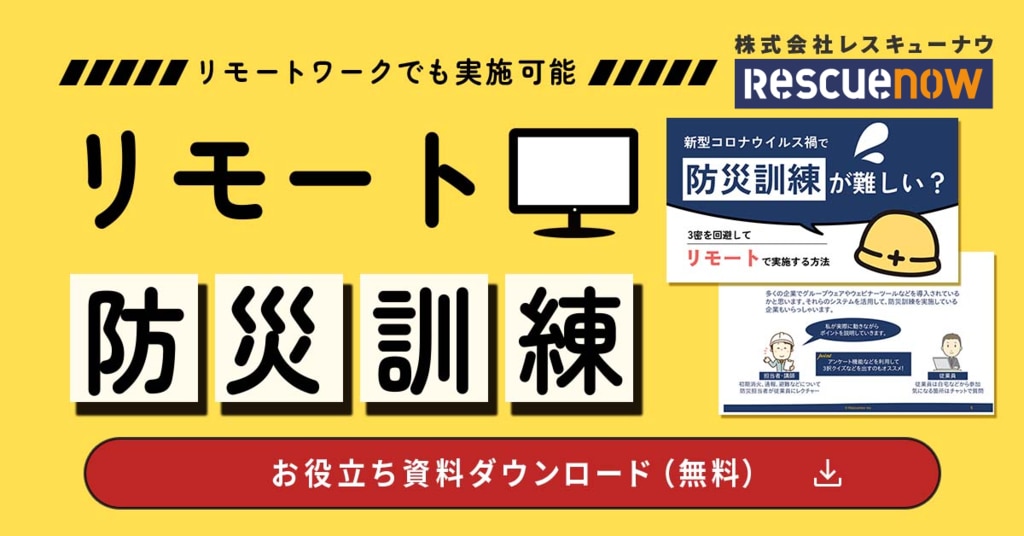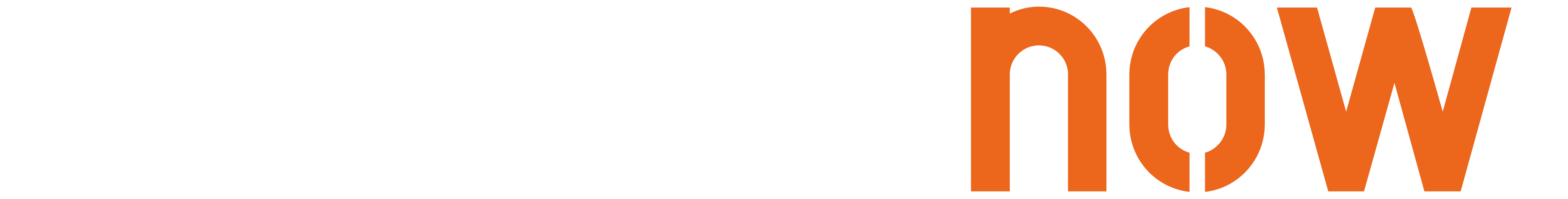災害時の避難場所に潜む脅威「感染症」から身を守るには?
こんにちは、レスキューナウです。
災害に直面した際、身の安全を確保することを目的として、時には避難所や勤務先企業の事業所に避難することが必要な場合があります。
しかし、私たちの命と安全を守るための避難場所や一時滞在場所にもプライバシーの確保や衛生管理の難しさなど、様々なリスクがあると聞くと、驚かれる方も多いのではないでしょうか。中でも注意したいのが感染症リスクです。
2020年の新型コロナウイルスの世界的な流行は記憶に新しいですが、その他にも風邪や季節性インフルエンザ、食中毒など、細菌やウイルス性の病気は数多く存在します。そして、避難所や一時避難場所といった限られた空間に多くの人が集まる場所ではこうした感染症のリスクが高まりやすいのです。
今回は避難所や一時滞在場所の感染症リスクという視点から災害に対する備えについて考えていきます。
▼ 事業所での帰宅困難者対策、できていますか?
この記事の目次[非表示]
なぜ避難場所で感染症リスクが高まるのか?
なぜ、避難場所では感染症リスクが高まるのでしょうか。理由は大きく2つあります。
ひとつは物理的なものです。新型コロナウイルスの流行時によく「密閉」、「密集」、「密接」を避けてくださいといわれていたかと思います。「三密」という言葉もしきりに使われていました。大規模災害で安全に過ごす場所を奪われ、多くの人が身を寄せ合う避難所では「三密」が発生しやすくなり、感染症リスクが高まります。
もうひとつ精神的なものもリスクを高める要因として挙げられます。避難所というのは慣れない環境です。そこで長期間過ごすとなると、どうしてもストレスや疲労が蓄積し、免疫力が低下する原因になります。これもまた感染症リスクを高めるのです。
令和6年能登半島地震の避難所にみる感染症リスク
避難所で感染症リスクが顕在化した事例を1つみていきましょう。それは、2024年元日に石川県能登地方を震源に発生した「令和6年能登半島地震」の避難所におけるものです。
最大震度7の揺れとそれに伴う津波を観測する大災害のなか一命をとりとめた被災者たちですが、寒さが厳しい真冬に長く過酷な避難生活を余儀なくされました。
すると、先述したような、物理的・精神的な要因により感染症リスクが高まります。実際に、避難所では新型コロナウイルスなどの呼吸器感染症、ノロウイルスなどの消化器感染症、咽頭結膜熱 の患者が発生し、さらには「クラスター」といわれる集団感染が起きた避難所もありました。
(参考)国立健康危機管理研究機構の能登半島地震に対するリスクアセスメント表
感染症のリスクは季節を問わない
令和6年能登半島地震は真冬の季節に起きた災害でしたが、もし7月や8月といった真夏の時期に、大きな地震や台風、梅雨前線による風水害などが発生した場合の感染症リスクはどう考えればよいでしょうか。
結論から言えば、感染症リスクは季節を問いません。
一般的に、気温が低く空気が乾燥する冬は、ウイルスの活動が活発になり、風邪やインフルエンザなどを発症しやすくなります。一方で、夏は気温が高く蒸し暑いため、咽頭結膜炎をはじめとするいわゆる「夏風邪」にかかりやすくなります。また、高温多湿の環境では細菌が繁殖しやすく、食中毒にも特に注意が必要です。
さらに夏の場合やっかいなのは暑さと湿度です。よく、感染症予防のためにマスク着用が奨励されますが、暑くて汗をたくさんかく夏場の場合、我慢してマスクを着用すれば、熱中症にかかってしまう危険性があります。そのため、マスクの着用も徹底するのが難しいのことも、夏の感染症予防には難しい点です。
(参考)夏に気をつけたい感染症について
(国立国際医療研究センター病院発行、タイトル「夏に気をつけたい感染症は「夏かぜ」「とびひ」「食中毒」夏かぜに抗菌薬は効果がありません 」)
進む避難所の感染対策とは
では、避難所で高まりやすい感染症リスクに対し、どのような対策を行うべきなのでしょうか。まず、避難所で進められている感染症対策を紹介します。
現在、多くの自治体では、過去の災害を教訓にして様々な感染症対策を避難所運営計画に盛り込んでいます。例えば、消毒液やマスクの配布、定期的な換気の実施、避難者同士の距離を保つ間仕切りや発熱者専用のエリアの設置といったものです。こうした対策も企業の防災備蓄品のヒントになります。
また、内閣府は令和6年能登半島地震での避難所運営を教訓とし、昨年末に自治体向けの避難所に関する取組指針・ガイドラインの改定を行いました。そのなかには、トイレトレーラーなどの確保・管理や入浴や洗濯のための生活用水の確保による衛生環境向上や、食事の質の確保、生活空間の確保が含まれています。現在、新たなガイドラインを参考にした自治体の動きも見受けられ、東京都では今年3月に避難所運営方針が策定されました。
災害時には企業でも感染症リスクが高まる
そして、このリスクの高まりは避難所だけではなく、皆さんが普段働いている事業所でも高まる可能性があります。
災害時、事業所の設備が十分に使えるとは限りません。例えば、断水や停電などライフラインにも大きな影響が出る可能性は十分にあります。そうすると、換気が不十分になる、トイレが使えなくなるといった事態が発生し、衛生環境の悪化で感染症リスクが高まります。実際、先ほど挙げた令和6年能登半島地震の感染症流行も、衛生環境の悪化に由来する部分があったようです。
つまり、都市部で発生する帰宅困難者の一時滞在による「三密」の発生はもちろん、一部ライフラインが使えない状況での事業継続でも感染症リスクが高まるわけです。
▼ 感染症が企業活動に与える影響とは?
企業で必要となる災害時の感染症対策とは
では、災害への備えの中に感染症リスクも織り込む上で、企業が取るべき行動はどんなものがあるでしょうか。それは、社内に一時滞在者や避難者が発生したことを想定し、事業所ごとにシミュレーションして備えることです。
災害時、事業所内で体調不良者が出たらどうするか、検討できていますか?
感染症対策も踏まえたシミュレーションとはどのようなものでしょうか。それは、ライフラインが止まった想定で、感染症対策、暑さ・寒さ対策などを考えていくことです。そして、感染症は、防ぐだけでなく広げないことも重要です。もし、事業所内の一時滞在者や避難者の中に体調不良者が出た場合、どうするか考えておくことも大切です。
また、災害時は皆大変ということで体調が悪くても我慢してしまう人も出てしまうかもしれません。そういう想定で定期的な健康確認を行うかどうかもシミュレーションの内容として検討してもよいかもしれません。
そして、シミュレーションする中で、自然と備えるべきもの、優先すべきものがわかっていくかと思います。はじめから完璧な備えは難しいです。少人数、短時間でのシミュレーションから小さくはじめて、徐々にステップアップしていくことをおすすめします。
「便袋」は必須!感染症対策になる備蓄品の例
シミュレーションをしながら事業所の災害対応や防災備蓄品を整えていく中で、感染症リスクを織り込むには何を備えるべきかを考えることに困難を感じる方もいると思います。そこで、感染症対策になる備蓄品の例を3つ挙げていきます。
最初に挙げるは便袋やトイレです。断水や停電で水道が使えなくなった場合、トイレの心配が出てきます。食べるのは多少我慢できるかもしれませんが、排泄を我慢することは大変難しいため、便袋や簡易トイレの備蓄は非常に重要です。よく、企業での防災備蓄は水の次に食事の確保が優先されがちですが、水と同じかそれ以上に排泄に対する備えが重要という意識が大切です。
次に挙げるのは消毒液です。感染症の基本的対策として「手洗い」は非常に重要です。断水の場合は手洗いができませんので、消毒液やウエットティッシュ、あるいは通常のティッシュも衛生環境を保つためには重要です。
最後に挙げるのはマスクです。感染症の基本的対策として、「手洗い」と共に「マスクの着用を含む咳エチケット」が挙げられます。このことからマスクを備蓄してもよいでしょう。地震の場合は倒壊や火災などで発生する粉塵から体を守るのにも重要な役割を果たします。
▼ 除菌剤に関する情報はこちら
▼ レスキューナウの防災備蓄品オンラインショップでは衛生用品も取り扱っています
避難場所での感染症リスクを低減するために
本記事では、災害時に命を守るために避難した場所であっても、感染症リスクとも隣り合わせの環境にあることを紹介してきました。
感染症は目に見えない脅威といえますが、事前に知識を身につけ、備えをしておくことで、その被害を最小限に抑えることは可能です。いつどのような形で発生するか分からない災害によって避難生活を余儀なくされた際にも安心して過ごせるよう、感染症に関する正しい知識を持つことも防災のためには重要です。
それぞれの大切な命と健康を守るため、多角的な視点から対策を考え、今できることから行動に移しましょう。
▼ レスキューナウでは企業向けの防災備蓄相談窓口を開設しています(利用は無料です)